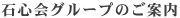


『課題と視点』をどう読むか
- 正しい高齢者医療改革に向けて -
石井 暎禧 ・ 横内 正利 ・ 滝上宗次郎
厚生労働省は、この三月に、長文の『課題と視点』を発表しました。
しかし、よく読むと、その主張は「はじめに」の⑥だけです。
つまり、「医療費の伸びが経済の動向とバランスのとれたものとなるよう」という部分だけです。
言い換えれば、高齢者人口が急増するが、経済成長が期待できないので、総医療費は伸ばさない、という主張です。
高齢者一人当たりの医療費は、年々削減していくという意味です。
さらに危険なことは、『課題と視点』は、高齢者医療に対する認識が浅く、短絡している。
現状は、大量の社会的入院が温存される一方で、高齢者医療のあるべき姿からどんどん遠ざかっているのです。
このままで、一人当たりの医療費が削減されていくと、医療はもはや責任を果たすことができません。
とても心配です。
そこで取り敢えず、真の高齢者医療とは何か、を語り合いました。
読者の皆様は、『課題と視点』がどれほど危険を含むものであるかを知ることでしょう。
そして、真の高齢化対策とは何か。実に簡単なことだと知るでしょう。
滝上
国民は、将来に強い不安をもっています。
そして、それが大きな社会問題となり、政治への期待は失われ、経済は消費や雇用が低迷しています。
こうしたなかで、増大する社会保障が危機の原因である、と語られています。
社会保障制度を維持したいならば、一にも二にも、老人医療費の膨張をおさえ込むことが緊急の「課題と視点」である、というロジックがいつの間にか世論となってしまいました。
老人医療費が膨張を続ける主因は、老人人口が増えることにあります。
となれば、老人人口の伸びをどうしたら抑えられるのか、というテーマと、意味するところはイコールです。
今のところは、「健康な老人は生命の質が高い」という表現にとどまっています。
しかし、これが世間にいきわたれば、生命の質の低い老人には、医療を受けずに、早く死んでほしいということに、すり替えられていくのでしょう。
九〇年代は失われた十年だった、とよく語られます。
要は、人災ということです。
重大な問題は、今後の十年もまた失われそうだ、という嫌な予感が日増しに強くなってきたことです。
日本経済は、僅かなプラス成長を維持するためだけでも、年々、数十兆円の借金を中央と地方の政府が増やしている。
海外の格付け機関は、相次いで日本の国債を格下げしました。
それでも、今はまだ国内資金によって国債は買い支えられている。
しかし、国内の資金には限度があり、いずれ破綻し、幕が降りるときがやってくる。
人災が重なっていますが、政治は責任をとる気配はありません。
代案として、意図的な大インフレによって家計を破壊するか、生命の切捨てである老人人口淘汰が、行き着く先となるのかもしれません。
美しい言葉がたくさん用意されてきた
滝上
今日は、生命の質について、議論いただきたいと思います。
最近、「苦痛だけの治療はやめよう」とか、「生きている時間が多少短くなっても、QOLや生き甲斐を重視したほうがいい」という声があちこちで高まってきました。
あるいは、「自己決定」や「ピンピンコロリ(PPK)」という言葉もよく使われています。
どれも気持ちのいい言葉です。
突然、この国は、人間を大切に考え始めたような雰囲気が、やたらと用意されてきました。
ナチズムの初期に似ているようです。
厚生行政をふりかえると、気持ちのいい言葉が出てくるときは、何かありました。
八五年に大蔵省に中島義雄主計官が登場してきて、医療費の伸びは経済成長の範囲内だといわれて、医療費は強く抑制されました。
あの時も、「医療費の適正化」という言葉に、すり替えられました。
適正化という言葉を使ったものですから、国民には違和感がなかった。
言葉は暴力だと思います。
ヨーロッパでは個室で介護されて当たり前です。
日本では、なぜ個室が極めて少ないのかというと、「相部屋」と呼んでいる。
相部屋というと、何か罪悪感が薄れるからです。
もし、「雑居部屋」「たこ部屋」と呼びなさいと言ったら、働く側にとって恥ずかしいし、うちは雑居部屋が何部屋あります、などとはとても言えませんから、自ずから個室に直っていくのではないかと思います。
介護保険もそうです。
介護保険が、いいか悪いかは次回に述べるとして、「利用者本位」だと言われ、「措置」から「契約」だと言われてきた。
すなわち利用者の側に選択権があるのだといわれてきた。
しかし、実態はそうなっていないと思います。
麗しい言葉が流れてくるときには、改革ではなくて、改悪なのではないか、と疑うことです。
国民は、注意しなければなりません。
理解されない高齢者に対する医療
横内
まさにその通りです。
社会保障の将来が危機的であると喧伝されるなかで、「人間的」であることが重視され、いやそれどころか、それが要求されるようになった。
このままいくと、人間的でない状態とか、尊厳のない状態とか、QOLが低い状態とかが、本人の認識を超えて社会的に規定されることになり、そのような状態の人は生きる価値がない、ということになってしまうのではないでしょうか。
なぜ状況が、ここまで一気に悪化してしまったかを考える前に、まず、高齢者医療の位置付けについて、整理しておきたいと思います。
一口に高齢者と言いますが、比較的若くて元気な高齢者は、基本的に非高齢者の延長と考えて対処しても、大きな問題はありません。
しかし、要介護や要支援などの「弱い高齢者」では、全く違ったアプローチが必要です。
もちろん、医療の理念自体は変わるものではなく、違うのは主として技術的な面です。
このような「弱い高齢者」に対する医療のあり方は、実はまだ確立していないのです。
確立しないで、混乱しているうちに、いつの間にか、医療技術の問題がQOLの問題にすり替えられ、「QOLの低い状態で生きることは無意味」といった、高齢者の生存権を否定するような議論が、急速に広まりつつあります。
たしかに、保険財政が限界にきて、医療費の伸びを抑えなければならなくなったことは、日本社会の重大な局面です。
最近は、あらゆる議論がまず、高齢者医療費の削減ありき、というところから始まっています。
しかし、そこに大きな落とし穴が待っているように思われてなりません。
その危惧の一つが、いわゆるターミナルケア、終末期医療に表れています。
「弱い高齢者」に対する医療のあり方が確立されずに混乱しているなかで、最も国民に理解されにくい終末期が、集中的に一部の経済学者から狙い撃ちされているのです。
高齢者の終末期医療費が国民医療費膨張の元凶と、根拠もなく喧伝し、ついで、特養ホームのレベルの高齢者をすべて「終末期にある」と拡大解釈し、そこへの医療の提供を批判してくる。
つまりは、「弱い高齢者」への医療をいかに減らすか、なくすかという観点からしか考えていないのです。
このような考え方は、最近、医師の間にも浸透し始めています。
どのような医療が「弱い高齢者」にふさわしいかという視点は影を潜め、代わりに、QOLという「錦の御旗」のもとに、「弱い高齢者」の切り捨てにつながるような議論が、展開されてしまっています。
これまで高齢者を、研究や金儲けの対象としてしかみていなかった医師たち、それに、「弱い高齢者」を門前払いしていたような医師たちが、ここへ来て一斉に、安っぽいヒューマニズムを振りかざすようになりました。
それまで、患者や家族のQOLはほとんど顧みずに、「何が何でも延命」に凝り固まっていた医師たちは、一転して、「無意味な延命」を批判するようになりました。
ちょうど、終戦と同時にゴリゴリの軍国主義者が一夜にして「平和主義者」に豹変してしまったのとそっくりです。
しかし、地域で長年にわたって高齢者医療に携わってきた多くの医師には、そんなに安易で無責任な割り切り方はできません。
つねに、個々の事例ごとに、「このように対応したが、本当にこれでよかったのだろうか」と思い悩むものです。
それが臨床家の姿です。
そして、そのような事例の積み重ねから、新しい医療のあり方が少しずつ形作られていくのではないかと思います。
無責任な医師たちは、もし少しでも良心が残っているなら、高齢者医療についての自分の主張に見合うだけの経験を自分は有しているのだろうか、と自問自答してほしいものです。
終末期医療は無駄か
滝上
国も、大きく関与してきたことは極めて深刻だと思います。
昨年の秋に、医療経済研究機構は、優生思想に基づいたような老年医療観を政策的に打ち出してきました。
「終末期におけるケアに係わる制度及び政策に関する報告書」がそれです。
ケアが、いかにヒューマニズムであるかという一面のみを語ることによって、弱い高齢者の生存に不可欠な医療を遠ざけようと狙っています。
つまりは、医療も、介護も必要な弱い高齢者には、医療を、取り上げることで早く死んでほしい、という発想です。
こういう馬鹿げた発想を正当化するに当たり、実に、念の入った方法をとっている。
その仕掛けは、介護を独立した学問であるかのように見せかけることです。
介護を学問化したり、科学化する茶番は、意外にも、医療、福祉に働く医師以外の人々の間で多くのファンを得ているようです。
なぜ、ファンができるのか。
理由は、医師に抑えつけられていたという意識のある人々は、介護という学問に頼ることで、医療に頼らなくても仕事ができる、お年寄りを幸せにできる、と思い込むからでしょう。
まさに医療のパターナリズムへの批判を、逆手にとった見事な方法です。ただし、こんな馬鹿げた思い込みが簡単に発生するのですから、医療の側も反省が必要でしょう。
石井
医療や医者を批判するのは結構ですし、指摘される問題が事実であれば当然です。
しかし、論議は事実に基づいてしてもらいたいものです。
嘘も繰り返されれば、真実である、と人々は錯覚します。
医療保険改革を論ずる際にも、おかしな議論がはびこっています。
その一つは、「老人への過剰な医療」という問題です。「誤った医療」を批判しなければならないときに、「過剰な医療」と言い替えて批判することです。
これは事の本質をすり替えています。
かつての「薬漬けの老人医療」は、本当は過剰医療ではありません。
「誤った医療」なのです。
過剰だという批判に対しては、「薬漬け老人医療」をした医者も「一生懸命やったから、老人の健康を害した。だから、今はできるだけ薬を出さない医療をやっている」などと、ぬけぬけと弁明できます。
このような嘘を免責し、かれらの老人医療をモデルとして、推奨してきたのが厚生省ですし、老人には「薄い医療を」、と主張する人々が追随しています。
誤った医療をやったためのQOLの低下を、医療そのものの責任にすり替えているのです。
老人医療を抑制することがQOLを高める、という奇妙な主張の根拠にもなっています。
もう一つは、老人医療費、なかんずく老人終末期医療費は無駄であり、高額だという問題です。
人は、終末期医療と聞くだけで、先の「過剰医療」批判がありますから、ナイーブに「無駄」と考えます。
「終末期医療に金をかけるな」という反応は当然です。
その上に高額だとくれば、医療はやめようと考えるのも自然の流れになります。
無駄と高額とでは、どちらが重要かというと、高額という問題です。
死ぬときぐらいは少々の無駄も認めよう、という考えがあり得るからです。
ところが、老人の死亡前の医療費が高い、という根拠は存在しないのです。
これは、社会保障・人口問題研究所の府川さんの論文でも明らかですし、私どもの病院の入院医療費分析でも明らかです。
老人終末期医療費による危機など存在するはずはありません。
高齢者医療イコール慢性期医療ではない
滝上
ようやく本題に入ることができるようになりました。
QOLという言葉は、最近までは「生活の質」として使われてきました。
それが、「生命の質」におき替えられてしまいました。
恐ろしい決意が国の側に透けて見られます。
横内
QOLについての問題も、底流には必ず医療費削減、医療の打ち切りというものがあります。
QOLの本来的な意味で議論されるのではなく、「QOLが低い状態であれば、医療を打ち切った方がいい」、つまり、「医療を打ち切った方がいい状態とは何か」が議論されることになります。
介護で、医療を代用することはできません。
医療を必要としている高齢者に対して医療を打ち切れば、どんなによい介護があっても、すぐに死んでしまうことが少なくありません。
とくに、急性疾患に対する医療が、重要です。
よく、高齢者には慢性疾患が多いので、高齢者医療とは慢性期医療のことだという人がいますが、とんでもない誤解です。
介護保険の対象になるような「弱い高齢者」は、多くの慢性疾患を抱えると同時に、種々の急性疾患にも罹りやすくなっています。
「弱い高齢者」の場合、脱水をはじめ、肺炎、尿路感染症、消化管出血など各種の急性疾患に陥ることが日常茶飯事です。
急性気管支炎だけでも、重大な呼吸不全を起こすことは少なくありません。
「弱い高齢者」の急性疾患の特徴は、「適切な治療があれば比較的容易に治癒するが、治療しなければ多くの場合死んでしまう」ということです。
この場合、補液(点滴)と抗生剤は必須の治療法です。
急性疾患のうち、最も注意を要するのが摂食困難による脱水です。
「弱い高齢者」に摂食困難がみられると、老衰とみられがちですが、多くは可逆的であり、治療によって比較的容易に改善します。
もし、摂食困難を老衰と決めつけ、適切な治療がなされなければ、高齢者を見殺しにすることになりかねません。
このような高齢者医療の基本が、残念ながら国民に正しく伝えられていないのです。
そのため、国民は、「QOLを維持・向上させるのは介護であって、医療は苦痛を与えるだけのものだ」という極端な議論を信じ込んでいます。
そうした極端な議論は、いったい何が狙いなのか。それは明白でしょう。つ
まり、急性疾患に対して積極的な治療が施されなければ、それだけ早期に死亡する人の数が増えるということです。
人間は一度しか死なない。
死んでしまえば、「弱い高齢者」への医療・福祉上の問題は、すべて消滅します。
莫大な経費節減になります。
治療すれば助かるかも知れない高齢者に対して、治療を控えることが、財政的には最も効果的です。
これは、たいへん危険なことです。
一般に、重度の要介護者が多いかどうかは、介護の質で決まると思われがちですが、その見方は正しくありません。
急性疾患の治療に熱心なところは、重度の要介護者を多く抱えることになる一方、急性疾患の治療に積極的でないところほど、重介護の高齢者が減少し、軽度ないし中等度の要介護者の割合が増加するはずです。
医療と介護は両方必要
石井
横内先生の言う通りですね。 「弱い高齢者」に対して、医療と介護が両方必要であるというのは、本当に当然のことなのです。 しかし、医療と介護のどちらをとるのか、あるいは医療と介護には代替性がある、といった発想が持ち込まれています。 QOLの重視や苦痛だけの医療をやめようということが、単純に「弱い高齢者」に当てはめられた場合、一気に医療をしないのが当然、というたいへん怖い社会状況が生まれつつあると感じます。
滝上
デンマークの弱い高齢者がまさにそうなのでしょう。
摂食困難になっても治療されず見殺しにされているようです。
ナチズムよりも早く、デンマークでは断種法が制定されたといった、北欧の福祉の真の姿をみてみようという新書が最近、相次いで出版されました。
デンマークの場合は、断種は、福祉のお世話を受けている人たちを対象に、実行されたといいます。
今のデンマークでも、福祉のお世話を受けている、高齢者への急性期の医療があまり見当たりません。
福祉の対象者を狙い打ちにするという、倫理感は昔も今も変わっていないのでしょう。
ロシア、ドイツ、フランス、イギリスといった大国に囲まれて、人口数百万人の小国が、歴史のなかを生き抜いてきたのです。
北欧の福祉が当然にもつ厳しさを、日本の一部のマスメディアは、意図的に隠して礼讃ばかりしてきました。
劣等な生命は淘汰されるべきだ、と主張し北欧の福祉を理論付けた、スウェーデン人のアルバ・ミュルダールは、一九八二年にノーベル賞を受けました。
しかも平和賞です。
北欧では、それは不思議なことではありません。
しかし日本では、国民がきちんと理解を始めれば、医療か介護かの二者択一の世論作りは、無理でしょう。
デンマークと日本では、死生観が違いすぎる。
現に、米海軍の士気のたるみによって、海底に沈んだ「えひめ丸」の引き上げをめぐって、日米の死生観の大きな違いが浮き彫りにされました。
日本と北欧では、さらに大きな開きがあります。
横内
医療と介護のどちらをとるのかという議論が出てきたことは、危険だと私も思います。
「弱い高齢者」のQOLのためには、医療も介護も必要です。
介護の目的はQOLである一方、医療は、むしろQOLを下げるもののように言われますが、医療の目指すところもQOLなのです。
いや、QOLの維持・向上は、医療の原点であり、本来的な使命なのです。
私たち臨床医は、患者さんのQOLのために、医療を実践しているのです。
最近、「医療はQOLについても配慮しなければならない」、「これからは、QOLが医療の目的になる」などと発言する医師たちがいますが、そのような医師たちは、これまで医療を何だと思っていたのでしょうか。私には、到底理解できません。
しかし、QOLは、本来個別のものであり、主観的にしか決まらないものです。
それを、無理矢理一般的な基準を作ったり、客観的に評価しようとしてしまうと、全く別の問題が発生します。
そして、それが高齢者を切り捨てる格好の口実を与えてしまいます。
老いて生き続けること自体がQOLが低い、という議論になってしまいます。
このように、QOLというのは素晴らしい言葉でありますが、それだからこそ悪用されると余計に危険な言葉になってしまうのです。
そこで、もう一度終末期医療に戻りたいと思います。
終末期の定義を曖昧にしたまま、「終末期では、QOLのためには医療を実施しないで死なせる方がよい」といった主張が目立ちます。
高齢者の終末期がきちんと定義できるのは、ほとんど癌の終末期に限られていて、しかも高齢者では、癌の終末期さえ、はっきり定義できない場合も多いのです。
癌以外の疾患の場合、終末期の定義はさらに難しい。
しかし、定義を曖昧にしたまま見切り発車をすることはきわめて危険です。
終末期を意図的に拡大解釈し、治癒の可能性が残っているものまで、「QOLのために医療を実施しないで死なせる」ことになりかねません。
現在、高齢者の終末期医療として語られているもののほとんどは、本当の終末期でない段階の話です。
つまり、終末期についての考え方を、終末期でない時期に、適用しようとしているのです。
高齢者の終末期医療はどうあるべきかを考える前に、高齢者の終末期をどうとらえるべきか、を議論すべきです。
そして、終末期がきちんと定義されるまでは、高齢者の終末期医療について不用意な議論をすべきではないと思います。
痴呆と死生観をどう考えるか
石井
「弱い高齢者」で特に問題になるのは、老人性痴呆患者の扱いです。
老人性痴呆は明らかに疾患ですが、治療方法はありません。
症状を軽くすること、QOLを高めるのはその患者への対応、介護、生活環境です。
この点をみると、老人性痴呆の問題は医療問題ではありませんし、老人性痴呆で死ぬこともありません。
その限りでは医療保険の問題ではなく、介護保険の問題です。
ところが介護保険では、「自立支援」を目的にしているので、自立できない痴呆患者を扱いかねているのです。
そのため、痴呆老人の扱いは、医者に任せるというのが、厚生省の逃げの口実です。
医療問題でない痴呆老人問題を、医療が解決できるはずはありません。
しかし、痴呆老人も他の病気にかかりますし、その治療は可能です。
ところが、痴呆が進んだ老人を痴呆の終末期といって医療に預けたため、ターミナルケアの概念はめちゃくちゃになりました。
そして、老人終末期だから、一切の医療をやめるべきだ、という意見が登場しました。
これは透析や老人病の学会を巻き込んで広がっていますから、ひどい話です。
痴呆老人問題は、最近の終末期医療論で登場した死生観というテーマの危うさを、浮き彫りにしていると思います。
本来ターミナルケアと、死生観は、何の関係もないと思います。
いかなる死生感を持っていても、QOLを高めることが医療であり、ターミナルケアに当たって、死生観は本人の問題として放っておけばよいことで、患者の死生観に他者である医療者は介入する必要はありません。
ところが、自己決定できない老人性痴呆患者の死生観は知る由もありませんし、痴呆老人への対応は、世間一般の価値観によらざるを得ません。
それに基づき医者や家族が対応を決めることになります。
死生観というテーマは、個人の問題ではなく、世間常識をある方向に誘導するために登場しているのです。
痴呆老人の生は価値のないものということになれば、死なせよう、ということになります。
QOLの翻訳が、「生活の質」から「生命の質」と変わるなかで、本人から見た治療への評価・選択を意味した言葉が、他人から見た生命の質の評価へと変わって来ました。
そのため、健常人が持っている障害者や病人への差別感から、「尊厳なき生命」を軽蔑し、自決を意味する死生観を持とう、と言う意見が表面化してきたのだと思います。
医療は苦痛を伴うもの
滝上
QOLという言葉が、悪用されたときの恐さはよくわかりました。
「苦痛だけの治療はやめよう」という最近のスローガンについては、医者としてどう考えていますか。
横内
滝上さんの二つ目の質問にお答えします。
「苦痛を与えるだけの治療はやめるべきだ」と最近言われ始めていますが、これは、「ある状況下での治療は、苦痛を与えるだけだから止めるべき」というところから出発しています。
ところが、その状況設定が合理的なものかどうかの議論はほとんどなされないまま、「苦痛を与えるだけの治療」という言葉が一人歩きをはじめ、「苦痛を与えるだけの治療は止めて、死なせるべきだ」ということになってしまっています。
しかし、その治療が本当に苦痛を与えるだけで、何の意味もないかどうかの検証は、ほとんどなされません。
一般的に言えば、医師は、意味があると思うから治療するのです。
はじめから苦痛を与えるだけとわかっている治療を、する医師がいるのでしょうか。
医療とは、元々苦痛を与えるものです。
体の悪いところにメスを入れるわけですし、薬物とは異物・毒物です。
もし、苦痛を与える医療は止めろというなら、医療自体が否定されることになります。
医療の目的は、命を救うこと、健康を回復すること、それに、QOLを改善させることです。
しかし、何の苦痛も与えずに治療することは困難です。
医療を行う過程と、その結果を、秤にかけて判断するしかないのです。
結果をみずに、医療を実施するときの苦痛だけを問題にするのは許されないことです。
必要なのは、「苦痛を与えるだけの治療は止めて、死なせる」ことではなく、「できるだけ苦痛を与えないように工夫する」ことです。
たとえば、医療行為中の身体抑制についても同様です。
もし、「絶対に抑制をしてはならない」というのであれば、点滴が実施できない高齢者が一定の割合で出てきてしまいます。
そして、その場合、死を選択することになりかねません。
医療現場での抑制は、福祉の現場で縛るなということとは異なります。
直接生死が関わることが少なくないからです。
もちろん、できるだけ抑制をせずに、必要な医療を実施しようという姿勢は必要です。
私たちも、いろいろな工夫や苦心をしています。
たとえば、二四時間の持続点滴は極力避けたり、筋肉注射に切り替えたりします。
心電図のモニターや尿カテーテルの留置も必要最小限にとどめます。
抑制をいかに少なくしてかつ治療効果をあげるかということこそ、私が最初に申し上げた、「弱い高齢者」にどのような医療を提供すべきかというテーマの一つなのです。
決して、「抑制を必要とする医療行為を止めて、死なせる」ことではありません。
そこのところを誤解しないでほしいと思います。
「苦痛を与えるだけの治療」と並んで、「無意味な延命」という言葉もよく使われますが、全く同様です。
「ある状況下で延命を図ることは無意味だ」という意味でしょうが、やはり、その状況設定が合理的なものかどうか、の議論はほとんどなされません。
そればかりか、まだ治癒の可能性が残っているにもかかわらず、安易に「延命」と決めつけられていることが多いのです。
つまり、「救命」というべきところを「延命」とみなされるのです。
滝上
横内先生は、医療の側も混乱していると言いましたが、石井先生がさきほど指摘したように、その原因は社会的入院によって病院を経営している医師たちにあると思います。
そもそも存立基盤のない、正当性のない老人病院が日本では大量に存在しています。
自分たちの存立を積極的に正当化するために、老人病院の経営者たちは、医療は過剰だと自己批判してみせたり、「縛るな」というヒューマニズムに満ちた運動を展開しています。
医療が医療を否定することに対して、一部のマスメディアが賛同して、大々的に繰り返して報道しています。
そのために、日本では真の老人医療に対する理解が確立せず、混乱しているのです。
福祉が不足しているために、社会的入院が大量にあることは容認されているのですが、変な発言や運動は困ったものです。
石井
無理解や誤解は多々あります。
痴呆の人に対する医療も、その痴呆の人は意味を理解していないのだから、やめた方がいいという暴論があります。
しかし、医療の現場でみると、医療を行う場合に痴呆の患者との人間関係がとれていれば、喜んでとはいわないが、受け入れてくれる。
そうでなければ、受け入れないというか、暴れてしまう。
われわれ医師に問われていることは、痴呆の人に対する医療の提供の仕方がどう工夫されているかです。
にもかかわらず、一気に痴呆の人に対する医療は意味がない、という極論が出てくることに医師として現状を強く憂慮しています。
そういう極論が、医療制度の危機のなかで出されてきた意味を、まず最初に認識しなければいけない。
一部の経済学者の医療への認識の浅さ、対案の安易さはひどいものです。
自己決定とリビングウィル
滝上
どうもありがとうございました。
次に、自己決定の問題に移ります。
この言葉は、デンマークを礼賛するときに使われた言葉ですが、それが最近になって、患者が本人自身の判断で、医療を拒否する、ことを賛美するという形で、自己決定という言葉が出てきている。
まず、自己決定あるいはリビングウィルというときに、私が子供の頃から言われてきたことは、悟りを開いた高僧が、たとえ今日死んでも大往生(この世を去り、極楽浄土に往って生まれること)といっていたのに、がんを告知されたとたんに、悟りなどどこかに消えていってしまってあわてふためいた、という有名な話があります。
そういう具合に、本来あやふやな問題についてどう思われますか。
石井
死の自己決定に限定して話すと、人間というものは死を選択できるのか、という根本の命題があります。
われわれが診ている患者をみても、死に場所も選択できない。
どのように死ぬかわからない。
事故で死ぬこともあるし、病院にくる途中であったり、病院から帰る途中であったりする。
病院、自宅、様々な死に方がある。
疾患にもよらないし、年齢によらないし、運命というか、神様の思し召しとしかいいようがない。
慢性疾患を長く患っていた人が、旅行先で急性疾患で突然亡くなってしまうこともある。
死というのは本来、自己決定はできないものです。
これをあえて自己決定するというのは、どういう狙いがあるのかと問いかけたい。
ですから、死の自己決定というのは、自殺というニュアンスをもってしか語られない。
最近は、自殺を自死という言葉に変えて、自分で自分の死を選ぶというようにぼかして使われます。
あたかも自然の死であるかのように。
だからこそ、死生観というものが問題にされるわけですね。
死が選べないなら、死に方という意味での死生観などというものはそもそも必要ない。
自分で自分を殺すという内容を含んではじめて、死に方という意味の死生観が問題になります。
しかし普通、死生観というのは、生き方の問題としてあるだろうと思います。
人生をより良く生きて、最後はそのことが現れる、という意味での死生観というのはよくわかりますが、死そのものを直線的に語るときには、やはり自殺というニュアンスを感じざるを得ません。
医者の側から自殺とは何かを考えると、はっきりいえば、広い意味の鬱病を先ず考えてしまいます。
現に自殺の九割は鬱病ではないかと言われたりします。
横内
その通りだと思います。
「弱い高齢者」の場合、鬱病以外の状況で人が積極的に死にたい、と思うようなことがどれだけあるのでしょうか。
基本的に人は死にたくはない存在です。
少なくとも本人の意思がわからないときは、「本人は死にたくないと思っている」と判断すべきです。
リビングウィルや事前指定の形で表示される自己意思も、その意味でかなり限界があります。
死や病気に直面する時点よりも、ずっと前の段階での意思表示だからです。
意思表示をしたときと、実際に死や病気に直面したときの気持ちとは、必ずしも一致しません。
それが最大の問題です。
しかも、「もう死にたい」とか、「早くお迎えが来ないか」と口癖のように言う高齢者はたいへん多いのですが、本心から死にたいと思っている人は、私の経験ではほとんどありません。
最近は、尊厳死宣言をしている高齢者も少なくありませんが、尊厳死宣言の意味や内容をどこまで理解して、宣言書に署名しているのか疑問に思うことがしばしばあります。
成人病は生活習慣病なのか
滝上
おっしゃるとおりかと思います。
私も、有料老人ホームを一五年経営してきましたが、そう思います。
というのは、有料老人ホームというのは健康な方々が入ってきて、徐々に体力を落としていって、急性疾患にかかりやすくなり、治療をしてもお亡くなりになることがあります。
やはり元気で医療をあまり意識していないときの、医療に対する意思表示と、体が弱って、年を越えて正月を何とか迎えたいとか、これから咲く桜の花をみてみたい、というときの医療に対する期待は、あまりに違うものです。
健康なときの、自己決定とかリビングウィル、事前指定書が、どれほどあやふやかというのがよくわかります。
一言でいえば、悟りを開いた高僧のようなものだと思います。
一つ問題提起をしたいのですが、苦しむのがいやだから、本人が自発的にリビングウィルを書いておくということがあるのですが、最近は他人からの強制が強く出てきました。
それは何かというと、あんな痴呆の状態になって生きてていいのかとか、要介護状態は生命の質が低いのではないか、という優生思想的な価値観を世間にばらまいておいて、そうなってはいやですよね、と世論を誘導している。
そうなったら治療はしないでくれ、といったリビングウィルを書けと促して、それがマスコミに載っている。
厚生労働省の健康日本21運動が、まさにそれです。
石井
滝上さんが問題提起している「健康寿命」とか「生活習慣病」という言葉には、確かに二面性があると思います。
一面では、生活習慣病とは、いい概念です。
例えば、糖尿病の人に療養指導するときに、これは生活習慣病だから食事に気をつけなさいと、非常に説得しやすくて便利な言葉です。
しかし、国がいままでは成人病といってきたのに、それを生活習慣病に代えたところに、非常に怪しげなものを感じます。
それは、生活習慣病にはもう一つのニュアンスがあって、「これは生活習慣なんだから、あなたの自己責任ですよ、自己責任である以上、こういう病気になっても、社会としては面倒をみる必要はないんじゃないでしょうか」というニュアンスです。
社会保険で治療を受けられないことがないように、「いまから生活を改めなさい」という一種の脅迫も含みながら、面倒をみない、ということを言おうとしているのではないでしょうか。
健康寿命もそうです。年をとって、健康でない者は自己責任である、と。
自己責任論は、さきほどの自己決定論と密接な関係があると思いますが、そうした枠組みで語られる。
ところが、生活習慣は一つの要素ですが、糖尿病にしても遺伝的因子があり、これは本人の自己責任ではない。
生活習慣病という言葉は、ものごとの一面であって、すべてではないことを理解して使わなければ危ういと思います。
滝上
同感です。
成人病という言葉が、生活習慣病にみごとにすり替えられた。
となると、病気の原因はどこかにあるのではなくて、本人の生活の中にある。
要するに自己責任だということですね。
社会保障の危機が語られるときに、自己の責任を全うできない人間にまで、僅かなパイを割り当てることはもはやできなくなった、という結論にたどりついていく。
結論を述べましょう。
老人の病気とは、生活習慣病であり慢性疾患が中心だと、厚生労働省は盛んに宣伝し、見事にそのような世論が形成されている。
となると次は、老人医療費が膨張する原因は、本人の健康管理の怠慢にあった、というロジックが形成されてしまいます。
そうした病人に、貴重な医療を提供する義務が、いったい社会の側にあるのだろうか。
…となれば、結論として、すべての老人医療を拒否できてしまう、ことが可能となってしまいます。
恐るべきロジックです。
世論の反対なく、第一段階として、老人医療費の自己負担を一気に上げることに成功するでしょう。
健康寿命という概念を振りまいている健康日本21は、まさしくそのための運動ですね。
当初は、厚生省が音頭をとっていたわけですが、堕落な生活をして何が悪いのか、一日一升の酒を飲んでもいいではないか、個人の自由だ、全員が聖人君子で生きるのか、といった批判が寄せられた。
それに加えて、戦争中のように国家管理でやるのかという批判もあって、国は対応できなくなってしまった。
そこで、今年に入ってから、健康日本21運動が行われているわけですが、厚生労働省は裏に隠れて、誰がみても健康そのものの著名人が先頭にたっています。
弱い高齢者を切り捨てるシナリオ
横内
健康寿命という言葉ほど怖いものはありません。
WHOの健康寿命の計算方法では、一時的に健康を損ねた期間が差し引かれているようですので、「何年間」と表現されるべきとも思われますが、日本では、「何歳」と表現されています。
健康寿命という表現は非常にわかりやすい。
わかりやすいだけにきわめて危険な言葉です。滝上さんが、はじめに「言葉は暴力」と言われたが、まさにその通りです。
健康でなくなったら、つまり、自立できなくなったら、寿命が尽きる、つまり死に等しいということです。
こんな差別的な言葉が、マスコミを賑わせるようになってしまいました。
当然、国の医療費抑制策や「弱い高齢者」の切り捨てに悪用されないはずはありません。
またしても、国民を欺く心地よい言葉が出現しました。
そして、健康寿命という概念の登場によって、「弱い高齢者」を切り捨てるシナリオは完成するのです。
健康寿命を「何歳まで健康でいられるか」の指標と捉えた場合、人間は、非高齢者→自立した高齢者→健康寿命の尽きた高齢者→終末期にある高齢者という段階を経て死に至ることになります。
そして、終末期の拡大解釈によって、健康寿命の尽きた高齢者は限りなく終末期に近い、ということになります。
これは、非高齢者や元気な高齢者の本音を端的に表現しています。
「弱い高齢者」は、終末期の拡大解釈と健康寿命という概念の導入によって、前後から挟み打ちされることになったのです。
加えて、今までみてきたように、「QOLの低い状態は生きる意味がない」、「無意味な延命は止めよう」、「苦痛を与えるだけの治療は止めよう」、「抑制が必要な医療は止めよう」といった考え方が追い打ちをかけます。
石井
健康寿命という言葉は、言っている人自身も自己矛盾に陥っているような気がします。
というのは、寿命が伸びるということは、健康寿命が伸びているから伸びるのです。
健康寿命が長くなって全体的に寿命が縮まるということはあり得ないわけです。
健康寿命が伸びたら、どうしても平均寿命は伸びます。
ますます老人は増えて、医療費はかかります。
健康寿命が伸びたら医療費は減らないのです。
医療費を減らすための健康寿命運動とは、健康でなくなったら、死ね、ということを強制でもしないと成立しない概念だと思います。
ピンピンコロリとぽっくり信仰の違い
滝上
石井先生の話に私も同感です。
私が気になるのは、PPK、つまりピンピンコロリです。というのも、健康寿命を長くしても、その後の要介護期間が目に見えて短くなるわけではない。
ということは、平均寿命そのものが伸びていって、年金財政はおかしくなるだろうし、決して健康寿命を伸ばすことが、社会保障費の削減にはならないわけです。
むしろ社会保障費を増やしてしまう。
となると、健康寿命を伸ばすことの裏には、第二段階として、老人医療を奪うことで、PPKでころりと死んでほしい、ということが同時にあるからです。
ピンピンコロリという考えは、もともとは上から政策的に与えられたものではなかった。
ぽっくり信仰はありましたが、それは個々の人々の願望であったわけですね。
それは、どんな人生を全うしたいかということであり、それはそれでいい価値観だと思います。
しかし、価値観は多様であって、要介護になっても長く生きたいという願望もあれば、ころりと死にたいという願望もある。
それは個々の人の自由です。
しかし、PPKという形で、上から価値の一元化が図られてくる。
あるいは、政府系の機関から報告書という形で出て来る。
これは、個人の自由への介入ではないかと思います。
介護保険の推進運動がはじまったときに、自立支援、自己決定という言葉が正面に出てきた。
こんな胡散臭い言葉はないなと思ったのです。
というのは要介護というのは、「自立」ではないということですし、自己決定という言葉とはそもそも対局にある概念だからです。
要するに自分で自分のことができなくなったから人に助けてもらう。
それが、日本の福祉の思想であって、また、死生観にもつながっている。
介護保険が出来たときに、「援助をする」といいながら片方で、「自立」であるとか、「自己決定」という言葉が用意されていた。
要するに完全に矛盾する言葉を同一の土俵に乗せてきた。
介護保険運動は、怪しいとしか思えません。
では、海外ではどうなのかと思って、ヨーロッパや北欧に詳しい人に聞いてみたのです。
私が、自己決定なんてできないでしょう、どうやって自己決定させて死なせるのですかと聞いたら、ずばり答えてくれました。
痴呆の人は自己決定などできません。
自己決定ができるというように社会が「みなす」のです。
自己決定ができるとみなして死んでもらうのです、とその人は答えた。
それを聞いて、みなすという言葉が、この世界にもあったのかと思いました。
一九九三年に横内先生が「みなし末期」という命名をされて、その後、この問題が終末期医療あるいは要介護者の医療のなかで中心的なテーマとなっているわけですが、やはりみなすという言葉はキーワードだと思います。
みなし末期とみなし自己決定
横内
みなし末期のほかに、みなし自己決定というものもあったのですね。
福祉先進国は、生死の問題も簡単に割りきってしまうのですね。
ところで、本人の自己意思であれば「延命拒否」は許されるということについては、多くの国民が合意しつつあると思います。
しかし、実はこのこともかなり注意してみていく必要がありそうです。
というのも、その次の段階として、その自己意思は客観化され、「延命を希望する人は少ない。
延命は意味がない」となりかねないからです。
そして、最後は、「延命してはならない」ということになります。
こうなれば、もうナチズムはすぐそこです。
実際、「延命を希望する」という家族の希望に対して、欧米では、翻意するように説得されるといいます。
いや、日本でも、延命を希望する家族に「延命の無意味さ」を説明し、延命を思いとどまらせる医師が増えているという。
しかも、このような説得は、延命についてだけでなく、救命についても、すなわち、治癒の可能性が残されている段階でも行われている可能性が高い。
となれば、もう日本にもナチズムが台頭し始めているといってもよいでしょう。
滝上
付言します。
自殺にいたった場合に多くが鬱病であるというご指摘は、私もそうかなと思います。
ただ、老人ホームにいて感ずることがある。
本人は死にたいと表現しているのだが、自殺しないケースです。
それは鬱病ということもあるが、要するに自分の生活環境を改善してほしいという要求が無意識に裏にある場合です。
だから、食事がまずいから生きていてもしょうがないとか、介護をきちんとしてくれないから生きていてもしょうがないなど、本人としては現状を肯定できない。
しかも、要介護の状態にあるから、自己の力で自発的に現状を改善できない。
そこにはあきらめしか残らないから、死にたいという言葉が出てくるのではないでしょうか。
そういう方々に対しては、どうやったら本来の意味でのQOLを高めることができるのか、といったことが必要です。
美しい言葉のように思われて、自己決定が安易に世の中で使われていますが、「死にたい」と言ったら、「死にたいのですね、では死なせてあげましょう」では反社会的だということです。
医療法人財団石心会 理事長
石井 暎禧(いしい えいき)
1937年、東京都生まれ。
1962年、東京大学医学部卒業。東京大学付属病院産婦人科へ入局。
1973年、石心会川崎幸病院院長、74年から現職。
1990年、石心会狭山病院院長を兼務。
役職は、日本医師会 医療経済・経営検討委員会委員、日本病院会 理事にて医療経済・税制委員会委員、地域医療研究会 世話人。
著書は、『医療と介護保険の境界』(雲母書房、共著)など。
いずみクリニック 院長
横内 正利(よこうち まさとし)
1946年、東京都生まれ。
1972年、東京大学医学部卒業。東京大学付属病院第3内科へ入局。
東京都老人総合研究所、国立循環器病センター内科医長、浴風会病院診療部長を経て、99年から現職。
専門は、循環器内科、老年医学。
著書は、『老年者心電図の読み方と実例』(医薬ジャーナル社)、『高齢者高血圧の病態と治療』(診断と治療社、共著)、『医療と介護保険の境界』(雲母書房、共著)など。
有料老人ホーム・グリーン東京 社長
滝上 宗次郎 (たきうえ そうじろう)
1952年、東京都生まれ。
1977年、一橋大学経済学部卒業。
三菱銀行調査部を経て、87年から現職。一橋大学経済学部、東京女子医科大学非常勤講師を兼務。
公職は、経済審議会「医療・福祉ワーキンググループ」座長、政府の行政改革委員会参与(厚生省担当)などを歴任。
著書は、『厚生行政の経済学』(勁草書房)、『終のすみかは、有料老人ホーム』(講談社)など。