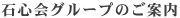


介護保険の持ち越された課題
介護保険法が成立し、制度の実施に向かって動き出している今日、制度への注文として言うべきことは、まだ決まっていない細部への注文だけでなく、あらためて制度の目指した基本の問題が、どのような方向で解決されようとしているのかを点検する必要がある。
様々な批判はあるものの、政府は、現代日本の高齢化に対応するには、介護の社会化を社会として認め、制度化しなくてはならないと認識していることは、紛れもない事実である。
これが介護保険を成立させた基本要因である。
そして介護保険の目指す方向として、高齢者の自立支援とノーマライゼーションがうたわれた。
提案された内容が、本当にそのような方向性を持っているのか否か、そのためには介護保険制度はどのような基盤整備と制度の仕組みを持たねばならないか、法案成立まで多くの議論が戦わされた。
基盤整備については、問題の性格上わかりやすい論点であり、「保険あって、給付なし」にならないようにという意見が出されるし、一般の人の関心も深い。
それと並んで重要なのは、制度が本当に機能するのかどうかである。
システムの基本問題が未だ十分には明らかにされていないことに注目すべきである。
介護保険制度が本当に在宅介護を進めるつもりがあるのか、とくに独居・日中独居の在宅介護は進めるつもりかが、問題の中心である。
介護度認定問題において、痴呆や虚弱問題が、解決しうるかどうか現場から疑問視されてきたのも、この点に関わる。
在宅介護と介護度認定
介護度認定については、一次判定と二次判定の適合率が70%であるのは、高いのか低いのかと論議されているが、厚生省は、やっていくうちに精度は上がる、認定問題はほぼ決着と認識しているようである。
しかし介護度認定の真の問題点は、精度ではないと思う。
厚生省の説明では一次と二次の判定の基準は同じ、(第二回目のモデル事業では)特記事項と医師の意見書によってのみ、一次判定の変更を認めるというやり方をした。
たしかに一次判定の精度問題は、調査員の能力と熟練度によってランクのばらつきはなくなるであろうし、二次判定が単なる微調整であるのなら、これでよい。
しかしモデル事業での意見書で、共通に指摘された問題は虚弱・痴呆の扱いと生活支援である。
いわゆる虚弱老人や軽度の痴呆への支援を考えると、家族内に介護者がいるケースは、もともとあまり問題はない。
独居者が問題なのだ。
介護保険の本音が家庭内に一人は介護するものがいることを前提に介護度認定をしている場合(支給額の水準として現れる)は、問題が生ずる。
言うまでもなく、介護度認定では、環境要素・家族要素は除外して認定するからである。
独居者や日中独居の場合には、ただちに在宅生活が不可能になる。
国の政策が在宅シフトであるのと矛盾するのである。
最近「介護保険は措置制度を否定するものではない、自治体は介護保険だけでなく、必要な福祉施策を用意すべき」と厚生省は注意を喚起している。
なぜならば必要な支援は狭義の生活支援であり、生計費との区分の難しい部分であり、環境要素として切り捨てられかねないからである。
これを全て自治体による上積み横だし給付によって解決できるのかどうか問題が多い。
この問題をみるとき、注目すべきなのは、今年度の医療費改定においては、デイケアについての制限が強化されたことである。
自立した高齢者へのデイケアの乱用は問題だが、重度の痴呆に限って毎日のデイケアを認めるとすれば、独居・日中独居の軽症者の在宅介護は不可能になり、全て介護施設に収容することになる。
これでは虚弱老人や軽度の痴呆の生活能力を一気に低下させることにもなりかねない。
介護度認定の本質は、身体・精神機能の障害を単にカウントする事ではない。
生活能力の障害を明らかにすることにある。
これらの課題が事実上は判定委員会の特記事項と医師の意見書によって修正されることだけに期待するのは危険である。
時間的に判定委員会の能力を超え、形式に流れる事態になる。
一次判定の内容が一層生活能力を判定しうるものになるべきだし、ブッラックボックスのプログラムの係数いじるだけでは、改善できないであろう。
医療と介護
介護保険の成立過程の論争で、わたくしは法案の骨格構造の変質に警告をしてきた。
本来の介護保険の構造では、「要介護者」への「介護」の給付であった。
ところが、法案が表に出るまでの間に二転三転し、第一条目的規定をみるかぎり「加齢に伴う疾病により介護を要する者」に「介護と医療」を給付すると変化した。
このような変化が生じた理由は、老人における介護と医療の区分が明確に認識されていないことと、社会的入院という事実に歪められたからである。
その結果、具体的なシステムの構築に当たって、様々な問題が生じてきている。
老人のケアを考える場合、そのケアの内容は医療ケア、生活ケアに分けられる。
生活ケアと健常者も購入するサービスとの区分は、実務的には切り放せないものがあるのは事実である、そのため介護保険の審議過程でも、介護保険の給付範囲を家事援助は含むのかどうか、給食サービスはと議論された。
しかしこれを金銭的・概念的に区分することは容易である。
同一の成果を持つサービスについて、健常者を越える付加的サービスあるいは費用を生活的ケアと考えればよいだけだからである。
誤った議論の進め方によって給食サービスははずれた。
サービスの項目をとりあげて、生活費か介護費用かと論じても無意味なのである。
先に見たように、介護の社会化を在宅介護にシフトしていくためには、独居老人のケアこそ問題であって、給食サービスも重要な要素である。
ヘルパー派遣によって食事を作るか、給食宅配をするかいずれかをしない限り、食事を作れない老人は生きられない。
しかし介護費用の一律1割負担に固執する限りは、食事サービスを介護費用に含めることはできない。
このジレンマが横だし上乗せ給付論であって、本来は介護保険の中に位置づけるべき問題だったのである。
このように行政技術論が保険制度の原則を歪めているのは、生活ケアだけの問題ではない。
医療と介護の区分をめぐっては未だに原則は明らかにされない。
制度の根幹構造をしっかりとしたものにするには、給付サービスと費用財源を対応関係を厳密にし、予想されない問題に対する原則的な対応が容易にできるよう制度設計すべきである。
医療ケアのコストは医療保険から、介護(生活ケア)のコストは介護保険から、ホテルコスト(狭義の生活費用)は自費または年金相殺でとなるべきであろう。
この原則が日本介護保険では曖昧になっている。
わたくしが問題にしてきたのはこの点である。
ところが、医療費の名の下に、介護費用を捻出してきた社会的入院の存在は、事実上の介護施設の費用の一切を介護保険でまかなうという、「現実的」ではあるが非論理的な制度設計(一施設2枚のレセプトは困るなどという枝葉の議論を含め)を強行した。
かくてわが国ではケア提供機関単位で医療保険・介護保険適用を分けるという奇妙な制度になってしまった。
これに対し、ドイツではソーシャルステーションの提供するケアについて、一般ケアは介護保険で医療ケアは医療保険でと、行為区分によって費用の出所は2つである。
わが国の原理を無視したご都合主義は病膏肓で、厚生省は現実に流され、医療の専門性を守るはずの日本医師会は、医療財源が介護保険財源にまで拡大することを期待して、介護保険の中で介護施設における医療費をまかなうことを求めた。
この結果、老健施設ですでに問題になっているように、介護施設に居住する老人たちの医療が保障できない構造は強化された。
医療保険の被保険者が医療保険を使えないと言う矛盾をなぜ誰も問題にしないのであろうか。
この問題とは別のようだが、認定システムをめぐり、MDS-HCを採用すべきであるとの川淵氏らの論説があるが、これも介護と医療の混同に基づいた主張に過ぎない。
医療と介護の両制度において、老人ケアにおいて医療と介護が未分化である福祉後進国であるアメリカの制度を日本がまねることはない。
主張すべきは介護認定で医療的観点を入れさせることではなく、医療そのものの必要を主張すべきなのである。
このように介護保険の成立と医療保険改革の中で、医療と介護の非分離が老人の医療の権利を侵そうとしている。
老人のターミナルケアの論争の中で、「老人(とくに後期高齢者や痴呆老人)には、医療は必要ない、介護があればよい」とする主張が「福祉のターミナルケア」と称して、過剰医療批判の俗論に乗りながら、広井氏らによって主張され始めているのは、このような制度の歪みと関連して、きわめて注目すべきだと思う。