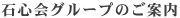


老人への医療は無意味か
老人への医療は無意味か
平成9年は、介護保険の成立、医療保険抜本改革案、福祉基礎構造改革案の発表など、一連の医療福祉改革案が登場し、医療・福祉の大変革がすすんだ年である。
この年に、医療と介護の関係の核心に触れる、老人のターミナルケアの問題について、報告書が出されたのも時代の必然であろう。
その報告書の著者の一人として、「老人医療介護保険」の提唱者である千葉大学の広井良典助教授の名が登場したのも偶然とは思えない。
しかし近年の広井氏の論説(生活モデル論)には、われわれ地域医療の現場のものとして、共感と危惧を織りまぜて感じてきた。
その危惧がこの報告書でいっそう深まった。
この報告書とは財団法人長寿社会開発センターより出された『「福祉のターミナルケア」に関する調査研究事業報告書』(以下報告書と記す)である。
報告書をはじめて知ったのは、友人から送られた報告書の第1章『「福祉のターミナルケア」の課題と展望』と称する竹中文良日赤看護大学教授の論文(以下竹中論文と記す)のコピーによってである。
読んでみて唖然とした。
超高齢者・痴呆老人が、病気になった場合、「医療をひかえ自然の成り行きに任せる」ことが「福祉のターミナルケア」のあり方として提案されているではないか。
竹中論文の結論をみる限り、「日本にもナチスはいるんですね」とのコピーに付された友人のコメントを肯定せざるを得ない。
だがそれにしても、「ターミナルケア」という概念がなんと安易に使われているのだろうか。
医療現場においては具体的ケアにあたって、「ターミナルケア」という概念は慎重に使われている。
ガン末期のケアの場合「緩和ケア」がもっぱら使われ、老衰の末期については、家族が介護する「在宅ターミナルケア」の場合は使われるが、病棟でのケアについて、安易に「ターミナルケア」という用語が使われない。
これは医療者にとって末期認定が持つ重さを感じているからである。
その後報告書全文を手に入れて読んでみて、竹中氏の書いた部分だけではなく報告書全体が問題だと感じた。
他の人々は、竹中氏ほど直裁に痴呆老人等への医療を否定していない。
しかし医療と介護の違い、慢性疾患への理解不足が、竹中論文を補強して、報告書全体として、痴呆老人や超高齢者への医療の疑問となり、結果として痴呆老人・超高齢者の生存権を否定する内容となっている。
報告書の構成と問題点
この報告書は4章の構成をとり、現状の医療に担われたターミナルケア(概念規定は不明確)への懐疑を持つ筆者らが、福祉の場におけるターミナルケアを期待するという構成となっている。
しかしその内容は、老人への医療の否定だけで、あるべき福祉のターミナルの像は浮かび上がってこない。
竹中氏による第1章は(「福祉のターミナルケア」の課題と展望)と題され、総論・結論の位置を与えられている。
「高齢者に関して医療をどこまで展開するか」が「医療者を悩ましている」と「課題」が語られる。
「展望」として、「年齢によって医療行為を中止する法律を作るのは行き過ぎだが」と法律的な強制は一応否定しつつ、「高齢者に対する医療を単純化する」こと、具体的には「死に行く者への吸引や酸素吸入は無効であり、“自然な死”に導くことに力を注ぐ」よう、法律によらない実践のすすめが暗示される。
竹中論文の文脈では、「死に行く者」とは、具体的には超高齢者・痴呆老人であり、「死に導く」ことの実践にあたり我が国では「個人的判断による具体的行為が難しい」との嘆きは、とりようによっては、殺人教唆を意味する(欧米の福祉施設において散発する職員による大量殺人事件を想起せよ)。
広井氏による第2章(本調査の趣旨と結果の概要)は外国の実践と論理の紹介がなされている。
ライトモチーフは米独型(医療型ケア)と異なる、ヨーロッパにおける生活型ケアの紹介である(このタイプ論が正当かどうかも疑問だが)。
広井氏の場合、竹中氏とは違い、「福祉がターミナルの相当部分を担う」ことで、「ソーシャルニーズひいてはたましいのケア」の可能性の模索が「趣旨」・問題意識であったと思われる。
だが80歳以上の死を「天寿を全うした」と無条件に規定するとき、
あるいはスウェーデンにおいて「痴呆老人向けのグループホームでは、吸引や酸素吸入をできる限り行わず“自然な死”を、という考えのもとにケアが行われている」と疑問を持つことなく紹介するとき、
「できる限り」「行わず」とは“できる限り早く死なす”という意味しかなく、
持論であった老人医療における「生活モデルの医療」の提唱は、その弱点を拡大して“できるだけ早く死なすための”「医学的な介入の必要性の薄い死のあり方」の推奨に変化した。
第3章は(特別養護老人ホームにおけるターミナルケア期のトータルケアを目指して)と題する日本のあるホームの実践報告である。
「トータルケア」が主題であったはずであるが、
「4.さくらばホームが構築したターミナル期のトータルケアの実際」は、死期の予見、家族への連絡、葬儀の準備に終始し、生を高める、積極介護の実践は語られない。
「トータルケアを目指す」というのは、すくなくとも医療を必要とするとき、医療機関に送るのではなく、ホームでやれることがあるのではないかという立場で、積極的な関与と問題点(制度上の制約を含め)の指摘がなされるとわたくしは期待した。
ところが“報告された内容は、介護者による死期の予見の実践だけであり、医療を必要としないことの判定にすり替えられている。
死期の予見は医療者にとっても困難な問題であるにもかかわらず、介護者が行えるとする自負はよいが、例示されている「死期の予見」の症状は、医学的にみて疾病の発生あるいは、悪化にすぎず、不可逆的な臨死状態を意味するものではない。
第4章の鈴木玲子・広井良典氏の(ターミナルケアの経済評価)は、死亡前1年間の医療費用の分析である。
医療資源配分論を意図しての分析であろうが、「終末期医療は直前になるほど費用がかかる」という、はじめから結論がでていることの確認にすぎない。
一年も前から死期の予想ができるはずがない以上、死亡時から逆算した経済分析(結果論)という方法は、意志決定には全く意味がない。
したがって「福祉のトータルケア」の実践方針を示す参考にはならない。
そのうえ在宅と病院の費用比較は、要介護老人という医療的に雑多なグループを、同一な推計学的母集団と仮定するという、基礎的な誤りを犯している。
少なくとも使われた費用(支払いの名目でなく)に含まれる項目の同一性、疾患の構造・症度の分布の同一性が確保されなければ、意味のある分析とはいえない。老人病院における「医療費」は実際には介護費であり、老人病院に入院する目的は治療ではなく、介護であるのは常識である。
純粋に医療費(介護費用・生活費を含まない)を比較するのなら、疾患の構成を同一とする無理があるが多少の意味はあるだろう。
しかも純粋の医療費を比べてみても、通常、入院医療は回復を目的にしており、医療の不成功の結果としての死であるから、医療費がかかるのは当然である。
他方入院医療を必要としない在宅医療で費用がかからないのは当然で、比較は意味がない。
むしろ調査から明らかになっているのは、在宅同士、入院同士をくらべると、皮肉にも、より高額であるのは、年齢の低い者である。
本報告書の狙いに反し、末期医療費を問題にするのなら、超高齢者のそれではなく、より若い者の末期医療費であるのはあきらかであり、過剰医療対策は、年齢による差別対策ではなく、疾病ごとの医療標準の策定という、医療技術そのものの客観性の確立と適正化でなくてはならないことを示唆している。
この報告書全体の本来の意図は、「本調査のねらいとするターミナルケアのもつ積極的な広がり(一定期間以上の期間にわたる、メンタルな支援を含めたケア)」(広井)とあるように高齢者の終末期ケアのあるべき姿だったはずである。
そうであるならば、終末期の医療技術の適否や末期であることの見分け方などは論ずべき主題ではなく、痴呆老人のメンタルなケアとはなにであり、
どうすべきか、老人の生活の質を高めるとはなにか、それが実践される際の問題点・費用はどうかと、論じられなければならなかった。
しかし『本研究はあくまで「政策論」的な論議を中心とするものであったため』、医療費抑制を論拠づけることを急いだあまり、現在の「医療に偏ったケア」という現実に対置して、医療の否定として福祉のケアを語ることに終始している。
どこにも「メンタルな支援を含めたケア」の内容が具体的に語られたり提案されてはいない。
それどころか「福祉のターミナルケア」の問題を、「医療に偏って」論じてしまったところに根本のあやまりがある。
しかし医療技術を語るには、この報告者たちの老人医療への理解は、医師である竹中氏を含め十分とは言いがたい。
老人医療への適用される医療技術への判断を欠いたまま、医療的ケアを論じてしまったことが、問題設定における痴呆老人への偏見をあらわにすることになった。
「死に行く者」への「無駄な医療」の打ち切りという主張によって、老人医療費抑制を政策的に裏付けしようとして、報告書が強引な論理を展開したためである
ガン治療と老人医療の混同
「難治性の進行ガンや超高齢者のガンに対する広範な根治手術で患者が苦しむ例を数多く見てきたので、自然の成り行きにまかせた看取りに私は魅力を感じている」という全ての疾患を同一視するくだりに、氏の論旨の混乱が発している。
たしかに消化器ガンのターミナルにおいては、一般的に言って、「延命」のために、透析も人工呼吸も酸素吸入も吸引も「無意味」なことが多い。
これと対照的に、超高齢者・老人において、透析・人工呼吸・酸素療法・気道吸引を継続的に必要とする場合は、いずれも有効で、数時間・数日でなく、数カ月・数年の生存が可能になる。
こうした現実を無視して、これらの技術が医療的にみて「無意味」であると一方的に価値づけしたり、数年・数ヶ月という生存期間をターミナル期であり「無意味な延命」であるとするのは、生存権の否定でしかあるまい。
これらの医療技術に意味があるかどうかは、超高齢者医療の一般論として決められることではない。
個別症例における治療技術の適否の問題に過ぎないし、緩和ケアの問題とも別である。
緩和ケアは、「自然の成り行きにまかせた看取り」ではない。
緩和ケアはガンの治癒を目的とする治療を断念したとき、医療が果たすべき役割が存在しないのかという疑問に対して、生活の質の向上が目的たりうるし、その点で医療の役割があるという立場である。
さらに老衰の末期における医療的ケアは、ガンの緩和ケアとも違い、治療の断念を契機にしていない。竹中氏はこの差異を無視して論じている。
その上竹中氏は老人への急性期医療を主張するものを「生物としての宿命を無視した幼児的発想」の持ち主だとおのれの医療理解の水準に引き寄せ戯画化することにより、本人の老人医療の理解水準をさらけ出した。
慢性疾患への一般的理解不足と、老人医療(特に急性期)の実体を知らないという二重の理由が、竹中氏をしてガン治療への批判の論理を誤って適用拡大させたのである。
末期や臨死状況における医療行為が有効か無効かは、現場では常に苦渋の判断を迫られる問題である。
当事者でない者が軽々しく評価することは困難なことが多い。
その事例に即して判断・評価する以外にはない。
事例への評価抜きに(あるいは無意味との前提で)決め付けのは、ターミナルケア問題の深化には有効と思われない。
しかし、具体的論拠が明らかでない分、論理の筋が見えやすい。
「本音の部分で超高齢者の医療行為が若者と同じレベルで行われるべきだとは信じていまい」との主張が、竹中氏の思想を鮮明に浮き上がらせてくれた。
医療行為による侵襲の大きさが治療法の選択に影響することはあるが、これを「医療行為のレベル」に横滑りさせて主張するのは、老人にふさわしい医療を行おうとの主張とはならず、老人には金を使うなといっているだけだ。
「レベル」を問題にするとき、これは老人差別である。
老人を女性に置き換えてフェミニストに主張してみればすぐわかることだ。
治療すれば回復する老人患者に対して、適正な医療を受ける権利を否定しているだけなのである。
ついでに言って置くが、緩和ケアは医療の質であれ費用であれ「低いレベルの医療」を推賞しているわけではない。
氏の立論は、現場で緩和ケアを懸命に進めているものにとっても迷惑な話だ。
同様に「無意味な延命処置」という言葉が、一人歩きしているのは、竹中氏だけでなく、この報告書全体を性格づけるものである。
「無意味な」という形容詞が、「延命」に懸かるのか、それとも「処置」に懸かるのかで意味は違う。
前者であれば「無意味な延命」すなわち「無意味な生」を続けさせる「処置」の意味であり、後者であれば、「延命という目的には無効な」「無意味な処置」という意味になる。
通常「過剰医療」として批判されるのは、後者の例であろう。
ところがこの報告書では、一貫して前者の意味で用いられている。
竹中論文の2つの症例でも、書かれた諸要件に関する限り、明らかに「延命」効果としては有効な医療処置が疑問視されている。
第1例は老人痴呆の慢性腎不全患者ですでに3年続いている透析医療が、否定され、第2例では、同様に痴呆の嚥下障害患者への胃瘻造設が否定されている。
いずれも「意味のある」「延命処置」である。
つまり痴呆老人の生存が問題視されているのである。
「年齢や老化の程度による治療指針の差はほとんど論議の対象にならない」のは問題だというが、「論議の対象」にすべきは、年齢や老化により、いかなる治療手段が有効かという個別技術論である。
報告書の見解に反し、いかなる「年齢や老化度」の老人が生存すべきでないかという価値論が「論議されない」のは、日本社会の健全さの現れなのである。
高齢者の医療について、無知・無能力な一部の医師がいるとしても、それは医学教育の問題として論じればよい問題であり、ターミナルケアのあり方の問題ではないし、痴呆老人・超高齢者への医療が「過剰医療」であるとの批判に正当性を与えるものではない。
一般的な状況論としていえば、科学性に乏しい医療は、「過剰医療」と「粗診粗療」を同時に持つ構造をなしているものである。
急性期・慢性期医療における医療の担い手
(医療のパラダイムの転換とは何か)
医療技術のあり方を、その対象である患者の年齢で分けて価値付けすること自体が方法論として問題(老人差別論)をはらむことに、竹中氏も広井氏も全く気がついていない。
「医療者を悩ましているのは高齢者への医療である」「医療から福祉主体に移行させるターニングポイントはどこかという難問」という設問自体が誤りの出発点である。
広井氏が「後期高齢者の増加」を前提とすると『これからのターミナルケアにおいては、ノン・メディカルな、つまり医療的な介入の必要性の薄い「死」のあり方が確実に増え、言い換えれば、長期ケアないし「生活モデル」の延長線上にあるような、いわば「福祉的なターミナルケア」が非常に大きな位置を占めるようになるのではないか』と語るとき、広井氏の「薄い」と竹中氏の「単純化」は対応し、「医療の薄い長期ケア」の延長上に、老人のターミナルケアが構想される。
この考えの基本は、すでに広井氏の著書である「医療の経済学」において述べられているので、報告書だけでなく、広井理論全体の問題として考えてみたい。
医療技術から、医療構造を見るとき、急性期の医療と慢性期の医療での違いが重要である。
ところが広井氏の場合「今後の老人医療を考えるにあたって、老人の場合の疾患は(壮年期までの)「疾患」というよりむしろ「障害」としてとらえるべきではないか」、「老人医療の場面においては、これまでの若人を念頭に置いて「治療」を第一の目標とした「医療モデル」とは本質的に異なる「生活モデル」こそが求められる」(広井「医療の経済学」)と老人医療の問題を一面的に結論づけている。
さらに疾病に対しては治療機能(医療モデル)、障害に対しては介護機能(生活モデル)とケアを振り分け、老人医療を介護の比重が高く、医療の比重が低いケアと考えている。
しかし「生活の質の向上」は老人医療だけではなく、年齢を問わず(若人の場合でも)慢性疾患医療全体に当てはまる目標である。
むしろ若者と比べ老人には急性疾患も多い。
老人の場合、慢性疾患も急性疾患も多いのである。
したがって老人医療が慢性期医療に限られることを意味しない。
さらに「障害」ととらえることが、「介護」は必要だが「治療」を必要としないと理解するのも飛躍である。広井氏は「障害」の意味を見誤ったのである。
慢性疾患は、治癒する事がなく、一生続く疾病であり、一生続く医療が必要である。
慢性疾患医療では、疾病の治癒を目的にしてはいない。
欠けたあるいは歪んだ機能を補充・是正し、できるだけ良い状態を維持することが目的である。
この意味で疾病を「障害」ととらえるのは正しい。
だからこそ「障害」に対しては介護だけでなく持続的医療が必要なのだ。
竹中氏が問題にした「透析」を考えてみよう。慢性腎不全は慢性疾患で、加齢に伴って、透析患者は多くなっている。
慢性腎不全になれば「生理的正常状態の維持」も回復も望めない。
ただ透析によって、腎機能の一部が代替できるだけである。
この点で、医療技術という点からみると、手足の切断に対する義手義足と同様の「障害」にたいする医療である。
老眼にたいする眼鏡の場合のように、同一のカテゴリーに属するが、もはや医療との認識も薄れている「医療」も存在する。
このように「障害」に対するケアとしては、さまざまな濃淡の「医療」が存在する。
慢性腎不全における維持透析は入院医療の対象ではなく、日常生活を営みながら、医療を受けることになる。
これば慢性疾患医療の通常のモデルである。
慢性疾患の急性期は、急性疾患と同様の前の状態(正常なでも根治へでもない)への復帰を目的に治療される。
そしてその状態が持続するよう慢性期医療が持続するのである。竹中氏のように根治的治療という概念で老人の急性期の治療を論じ、否定するのはピントはずれであろう。
日本の疾病構造は慢性疾患中心になっている。
医療のために生活を犠牲にすることを当然とする急性疾患での医療のイメージは限界を持ってきている。
その点で広井氏が「長期ケアないし生活モデル」という問題を急性期のケアと違った角度で取り上げるのは理由があり、われわれも共感するところである。
しかし、透析医療で明らかなように「生活モデル」の中では「医療」が量的に薄いととらえるのは、問題の所在を誤らせる。
広井理論の基礎になった長谷川敏彦氏の「タイプ」論は、医療費の費用対応効果の問題としてであり、社会的な資源配分の問題である。
その限りで医療および介護への資源の最適な配分を考察するのは重要である。
しかし、老人への医療的ケアのあり方の議論としては問題の立て方が違う。
資源配分を問題にするのなら、社会的入院や不適切な薬剤使用など、老人への医療の制限以前に検討すべき課題はたくさんある。
しかも長谷川氏は、老人医療のタイプとして「急性ケア、予防的ケア、末期ケア、長期ケア」の4つをあげていることは、広井氏の著書の中でも明らかであり、しかも広井氏自身が「末期ケアは長期ケアより、医療の比重が上回る」と書いているのであるから、報告書で広井氏は老人医療イコール「生活モデル」という図式をたて「生活ケアの延長上の末期ケア」と見解を単純化して書きすぎたようである。
老人の急性期医療の重要性に対して、
広井氏は部分的問題として意図的に無視し、
竹中氏は老人への医療イコール「過剰医療」として、
“みなし末期”という言葉を使い「末期でない者を末期と見なすことは誤り」と批判した浴風会病院の横内氏「老人医療の問題点」(社会保険旬報1804~1806)を反批判して、「みなし末期」を肯定している。
この問題については老人医療の専門家である横内氏に譲り、彼らの論理構成の問題点をさらに明らかにしたい。
「政府の医療資源配分の優先づけとターミナルケア」の章におけるスウェーデン事例の引用の仕方も、同様に、意図的な引用だ。
「緩和的なターミナルケアはもっとも高い順位の一つに位置づけられている」と引用するが同一の最も高い順位に「致死的な急性疾患のケア」「放置すると恒久的な障害又は死に至る疾患のケア」「重度の慢性疾患の治療」および「自立性が損なわれた人のケア(意識障害、痴呆、知的障害、言語障害等)」が挙げられていることを、無視している。
いやむしろ、広井氏がスウェーデンの事例の全文を報告書に書き込みながら、このようにアンフェアーな引用に無自覚なのは、氏の思いこみが強すぎたとみるべきであろう。
「生活モデル」の発想は、資源配分のタイプとして考えるのでなく、医療の普遍的捉え方(パラダイム)として検討することで、はじめて意味のあることになると思われる。
医療を医者の目で見ることから、患者の目で見ることへ、すなわち医療を医者が管理する「入院医療モデル」から患者本人が管理する「生活モデル」という枠組みで考えること、いわゆるパラダイムの転換が必要になっている。
急性疾患・慢性疾患の全ての期を含んで医療を見るとき、医療の目的は「生活の質」を高めることであり、生活の一部である(老人医療のみを、「生活モデル」で考えることを広井氏はパラダイム転換というが、これはパラダイム転換ではなく分類にすぎない)。
このとき治療の主体は、医療者から患者本人にかわる。
医療者と患者の関係の変化、これが医療のパラダイム転換の実体なのだ。
こうしてはじめて、インフォームドコンセントの意義も明らかになる。
ケア内容への本人の理解と主体的参加なくして、インフォームドコンセントも「生活モデル」のケアもあり得るはずはない。
インフォームドコンセントを含むことによって、「急性ケア」も「生活モデル」というパラダイムの中の特殊型と理解できる。
「生活の質」の観点から、医療のあり方を類型的に考察する際には、医療と介護の量的考察というタイプ分けでなく、医療者と患者の関係論として、考察する方が実践的な意味がある。
これからの老人医療のあり方を考えるとき、われわれの病院の小野重五郎が「慢性疾患と自己管理医療」(社会保険旬報59・2・21号)で医療者と患者の関係から、1(急性・重症型)、2(共同型)、3(自己管理型)に分けて、慢性疾患医療のあるべき姿を考察した論文は、一つの示唆を与える。
もっぱら医療が医師に任され、患者は、説明され、納得する以上の役割を持たない急性・重症型。治療行為がもっぱら患者本人によって行われる自己管理型医療。
この中間として存在する一般の医療。自己管理型医療にあって医療者の役割は、疾病に直接関わるのでなく、患者に情報を与え教育するという言葉による働きかけを主とする。
慢性期の医療は、自己管理を理想型とする2型および3型医療である。
「長期ケアあるいは生活モデル」のケアの問題とは医療の濃淡ではなく、医療の主体の問題であり、ケア(医療や介護・生活支援)の場の問題であると、われわれは考える。
このように考えてくると、自立性が損なわれ意志決定の障害を持った痴呆老人へのケア(医療・生活の両面で)のあり方が、問題になる。
意志決定が施設の介護者側にあるとするなら、医療におけるこれまでの医療管理型の構造と全く変わらず、福祉施設においても、過剰ケア・過少ケアが成立し、老人の人権は省みられないことになる。
いま介護保険システムが成立するにあたって、成年後見制度が必須のものであることが、ようやく理解され始めたのもこの理由からである。
後見とは患者との関係性そのものの問題なのだ。ところが報告書では、このような問題意識はもたず、医療者・介護者側の恣意的な、末期の判断と生死の決定が、何の疑問もなく主張されている。
生死の問題さえも相手の立場に立った思考がなされていないところに、われわれは恐怖感をおぼえる。
慢性疾患の医療技術
(個別症例の持つ問題)
報告書における、慢性疾患の医療技術の意味についても、現実とは遊離した判断がなされているように思われる。
患者にとって医療が生活の質を低下させるような場合、延命か生活かの二者択一が迫られる(抗ガン剤投与の選択のように)のは当然であり、本人の選択である限り、延命を選ばないことは認められるべきであろう。
たとえ医療者側との判断の相違があっても、生命倫理にいう愚行権として認められるべきである。
「尊厳死」はこの文脈で承認されるべきであって、尊厳ある生がなにであるかが問題にされているのではない。
老人のターミナルケアにおける「延命技術」を同一の論理の中で論じ、意図的に混同しているのが、報告書であるように思われる。
超高齢者や痴呆老人にとって、この報告書で取り上げられているような「延命技術」すなわち持続的医療処置は、生活の質と矛盾するものではない。
身体の状態・生活の質を改善することを目的とするものである。
唯一問題があるとするなら、医療には費用がかかるといういう問題だけである。
竹中氏が痴呆老人の透析を問題視することは、この問題の真の所在を照らすものである。
かつて透析技術は急性腎不全にのみ適用される、きわめて“高度な”“複雑な”“高価な”急性期の医療技術であった。
いまや家庭透析が可能なように、一見複雑そうであるが、技術進歩・機械の自動化等により素人が医療行為者となれる「単純な」「延命技術」にすぎない。
昔と比べれば安価になってはいるが、多くの資源を使うことは間違いない。
しかしこれによって数日のうちに死亡する人が、普通の生活ができる状態になるのであるから、この費用の高さをもって老人透析の否定はできないし、高いといっても重度の介護費用と同水準である。
ALSにおける持続人工呼吸もまた同様な技術である。
さらに竹中氏が問題であると指摘する内視鏡下(腹腔鏡下ではない)のボタン式胃瘻造設術(PEG)は身体的侵襲が小さく15分程度でできる小手術にすぎない。
これまで苦しい経管栄養にたよっていた人が胃瘻になると笑顔がみられ、患者の生活の質は高まる。
米国では2週間以上の経管栄養はPEGに変えるように勧められている。
PEGのよいところは、体力が衰えて経口摂取ができなかったものも、これにより体力を回復し、再び経口摂取が可能になる場合があり、たとえ全量経口摂取ができなくても、併用が可能な点である。
そして、不要になれば、ただボタンを抜去すればよいだけで、必要になればまた作ればよいだけの簡便な技術である。
さらに家族の介護負担を軽減する効果もあり、経管栄養とは異なり病院への入院でなく、介護施設での生活が可能になる。
われわれはPEGをつけた老人を福祉施設が受け入れてくれるように努力している最中である。
しかるに、これらを問題視するのは、治療効果や医療コスト問題ではなく、老人のケアコストそのもの、さらには老人の生存そのものを問題にしていることが明らかである。
最近われわれは、病院にきた特別養護老人ホームの生活指導員から、「こんなこと(PEG)をするから、老人が死ななくて困る」といわれるという事件を経験した。
このような発想は報告書の著者たちだけではない。
呼吸器系の疾患に対する酸素吸入や吸引については、いうまでもなく、きわめて簡単かつ安価な医療技術であり、患者の苦しみを軽減する。
不必要な酸素吸入や吸引をやる必要がないのは当然として、必要な場合でも「できるだけやらないように」というのは、痴呆老人の場合でも疑問を持ってしかるべきではないだろうか。
意識レベルが不可逆的に低下した末期の状況に置ける医療の継続か断念かは、臨床現場で迷う問題である。
広井氏が取りあげた某新聞の「事件」と福祉現場の反応は、リビング・ウィルが明らかでない場合のとまどいを示している。
新聞も(消極的安楽死)の要件を満たしているか「極めて微妙」と報道している。
担当医師もこの問題を意識した上で、討議に参加して苦しい決断をしている。
この場合は判断が分かれるのはやむを得ない。
しかし報告書は本人の選択(リビング・ウィル)の問題の存在を意識せず、医療の評価もせず、末期の医療の断念を個別の経緯と状況を抜きに、老人一般論で行おうとするところに問題があるのだ。
介護(生活支援)の場と医療の役割
急性期医療と慢性期医療を区分することなく、老人ケアの問題を老人医療施設類型すなわち医療の濃度・比重と考え、政策の基礎にしてきた厚生省の失敗(社会的入院の増大)が問われている。
広井氏は「医療の経済学」において老人医療関連施設の体系として長谷川氏が作った表を引用している、ここでは不十分ながら、障害度と疾病度を2次元のベクトルに配置して一つの見識を示している(だが厚生省の政策はその立場を貫徹せず、一次元の施設類型の配置しか考えない)。
しかしかれらも実際上は療養型病床群、老人病院、老人保健施設、福祉施設を疾病度の大きさとした厚生省見解に依拠して考察したため、現状をはずれた空論となってしまった。
これらの施設の利用は、疾病度とも介護度とも関係なく、介護を必要とする老人への利便性によってのみ使い分けられている(施設類型ではなく個別施設の介護能力での使い分け)。
われわれの経験からも、本人の医療上の不安感という一点を除けば、在宅医療で管理している老人で、介護力が十分なうちは老人病院への入院が必要な患者はいないし、在宅では医療が難しい病人で老人病院において治療が可能な患者もいない。
横内氏の報告「有料老人ホーム利用者の入院実態」(社会保険旬報1997.10.21号)によれば、氏が関与している有料老人ホームで病気になった老人は、いずれも急性期病院で短期入院の後、直接ホームに帰っており、老人保健施設や療養型病床群の必要はなかったということである。
老人病院も老人保健施設も緊急入所ができることが、最大の利点である現実を広井氏らは知るべきであろう。
療養型病床群で介護能力以外で存在理由を獲得してきているのは、リハビリテーション施設として残ろうとしているところだけである。
老人保健施設にあっては、ポスト病院というより在宅介護支援のショートステイ施設として機能する事によってである。
福祉施設・介護施設において老人医療の問題から逃げないのは立派な態度であるが、それは医者の代わりに末期を見分けることではない。
在宅医療でできる程度の医療が、介護施設でできるようにすることであり、家族ができることをプロの介護者が医療だとして、手が出せないシステムを変えることである。
医療機関と連携するとは、安易に病院に送ることではなく施設での慢性期医療は在宅医療の一類型として考え共同してケアすることである。
広井氏の調査報告の中でも、福祉の現場からは、施設での医療が可能になってほしいとの声が出ているのを重視すべきなのである。
それなくしては、病気といえば、すぐに老人病院へ送り、さもなければ「自然の看取り」というのであれば、家族が最初から病院を選択するのは無理もない。
社会的入院は必然というべきであろう。
この点での広井氏の立場は動揺があるようだ。
ターミナルケアも介護の場でという問題意識は正しい、しかし方向は逆である。
現状では、老人の諸施設はいずれも介護(生活支援・身体介護)を主な目的として、運営されているにもかかわらず、医療行為の制限だけは医療の必要性と関わりなく制度化されている。
そのうえ疾病の種類、疾病度と関係なく医療費は施設類型ごとに定額と定められている。
これらは医療の不在、医療費の過剰と過少の共存であり、病気や障害を持つ老人への逆選別が日常化している。
建前上は病院から家庭に帰る中間施設として規定されている老人保健施設では、医療費の制約から慢性呼吸不全患者の持続酸素療法程度のこともできない。
特別養護老人ホームにたいしては「できるだけ外来通院も行わないように」という行政指導がなされている。
この現実を前に、「できるだけ酸素吸入をやらない」という福祉施設の方針は儀式の問題ではない。
現状の福祉施設のあり方を肯定し、一歩進んで、医療を否定し老人の抹殺を肯定する方針なのである。
ターミナルケアは「死に行く者」へのケアか
ケアの経済政策面からみると、老人ケアの問題点を「過剰医療」であるとし、「死に行く者」への「自然の看取り」を対置するのは状況への立ち遅れである。
老人医療における「薬漬け・検査漬け」は施設ケアに関する限り過去のものになりつつある。
老人病院の多くが「定額制」となり、残された「一般病院」における「長期ケア」も「定額制」になることは、医療保険改革厚生省案でも与党合意でも明らかである。
「定額制」においては、「過剰医療」だけでなく、医療そのものが、施設にとって経営的に負担となる。
老人ケアにおいて、医療・介護のいずれであっても費用・労力をかけないこと、あるいはケア度の高い老人を少なくするのが、経営の要諦となる。
ケア度の高い老人の長生きは、施設の経営にも、職員の労力の面でも迷惑となる。
福祉の現場から発せられる、自分の仕事を否定する過激な「老人は社会のお荷物、早く死ね」との言辞は、このフラストレーションの発現形態とみることができる。
他方、病床抑制と急性期病床の「慢性期病床」への転換が進み、急性期病床は減少しつつある。
老齢人口の増大を考えると、福祉・介護施設において、「医学的介入の必要性の薄い」要介護老人の比率が増えるのではなく「医学的介入の必要性の濃い」要介護老人が、実数でも比率でも増えることは確実である。
福祉の現場の矛盾は増大が予測される。
こう見ると「薄い医療」の提唱と「延命」批判は状況への立ち遅れどころか問題の核心へのゆがんだ形の「的確な」対策と言えるのかもしてない。
この報告書において「終末期医療費」と呼ばれているのは、老人医療費の別名にすぎない、終末期が死の1年も前からであるとしたら、そのような予測は不可能である以上、後期高齢者や、疾患や障害を持った高齢者はすべてターミナルとするほかないからだ。
「生活モデルのケア」は「生活に重点を置いたケア」の意味から「医療の薄いケア」に意味を変え、さらに「早く死なすケア」へと変化した。
無限定に老人を「死に行く者」と規定したため、医療を含む生活を営む人間の生を無視することになり、入院を含む必要な医療を過激に否定してしまった。
在宅や福祉施設での「医療の薄い」介護なら医療費が安くなると結論づけることを急ぎ、これをあるべきターミナルケア考え方であると端的に主張するにいたった。
「死に行く者」との安易な規定は「死すべき者」に容易に転化した。
竹中氏が老人という存在を「生物の宿命」という見地で理解していることは、この報告書から必然化する人間観を示す。
人間を文化・社会的存在と考えず、生物として考える限り、生殖年齢を超えた生物の存在は意味がない。
ジャングルの自然の中では、高齢の生物は生存できない、死に行く存在である。
ジャングルの自然への対抗物である医療という反自然が問題にされるのも当然である。
老人を人間として考えず、生物として考えるという発想は、文化・社会の衰退あるいは混乱の時代によく登場する。
戦後日本の社会・文化の後退と転換の時期に、深い考察に基づかない内容の報告書にすぎないとしても、この報告書が出された時代的意味は無視できない。
われわれは在宅・介護施設での看取りに積極的に協力しつつ、「死に行く者」ではなく「生活する者」への医療を、在宅での老人医療、ガンの終末期医療をすすめている。
その立場からみて、この報告書の主張を認めるわけにはいかない。